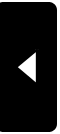2012年08月16日
*handmade*乙女なナチュラルレース蝶々*ヘアコーム*
★本日のおススメ商品★
うさぎ屋 で人気のく作家*le ciel*
で人気のく作家*le ciel*
カラフル
*handmade*乙女なナチュラルレース蝶々*ヘアコーム*
 handmade コーナー から
handmade コーナー から
オシャレなプレゼントに♪
ナチュラル
SWEET系(*/∀\*)
可愛い
*ハッピー♪
na乙女アクセがニクイ
可愛い個性派naいやし系
アンティーク感あり可愛いファッションのワンポイント♪に揃えたい****

ナチュラル
ナチュラルレースや蝶々のチャーム 可愛い♪癒される カラーです(*/∀\*)
可愛い♪癒される カラーです(*/∀\*)
乙女心くすぐるパーツ
手が込んでる★
¥800
かわいい(ノ´∀`*)
*SioMaNeKi*も欲しい一品ですな~♪


*SioMaNeKi*の豆知識
*髪飾り*
わが国では、古代から髪を飾る習慣があり、頭に挿すものを髻華(うず)、あるいは挿頭華(かざし)といい、また頭に巻くものを鬘(かつら)とよんだ。当初は自然のままの植物の花を使ったが、のち金属製のものとなった。男の場合は603年(推古天皇11)わが国に冠位制度ができたおりから、元日に髻華をつけることになった。のち皇子諸王諸臣はみな金髻華をつけたが、この制度が複雑化するにつれて銀、銅などが加わった。平安時代に宮中の年中行事が確立するとともに、宮中参内のおりに草花を飾りとしたが、冠や烏帽子(えぼし)の生活が日常化するにつれて、頭髪よりも被(かぶ)り物に飾りとしてつけた。もちろん、儀式、官位、身分によって一定の決まりがあった。
女性の場合は、飛鳥(あすか)・奈良時代に衣服令が定められて、礼服を着用するおりには宝髻(ほうけい)にしたが、平安時代以降になって、盛儀のときに着用する女房晴装束には、髪上げをしてから釵子(さいし)を飾りとした。庶民生活のなかで髪飾りが用いられるようになったのは、下げ髪にかわって、髷(まげ)のある髪形ができた江戸時代からである。まず最初に櫛(くし)、笄(こうがい)、簪(かんざし)が挿され、これに加えて手絡(てがら)、丈長紙(たけなががみ)、根掛(ねがけ)、はね元結(もとゆい)などが用いられた。遊里における花魁(おいらん)の姿の華やかさから、町人の粋姿(いきすがた)にまで髪飾りはその一役を担ったのである。
明治になり、日本髪より束髪が流行するようになって、日本的な髪飾りは一時減少した。明治末から大正初期にかけては松井須磨子(すまこ)が演じた『復活』にちなんで、ゴムの輪櫛(わぐし)が「カチューシャ」とよばれてふたたび少女たちの間で大流行した。第一次世界大戦後は断髪の流行やパーマネント・ウエーブの普及の余波を受けて、急速に髪飾りは減っている。しかし、正月などの晴れ着を着る際に新日本髪には髪飾りとしての花簪(はなかんざし)は必需品であり、打掛(うちかけ)姿の花嫁衣装には欠かせないものの一つでもある。
★インタネット引用より
昨日の*SioMaNeKi*ふぁっしょんは、
 イメージタイトル
イメージタイトル
「 *ピンクnaアマゾネス?!*」
 トップス⇒ピンクのタッセルペイズリーカットソー*Lablynth
トップス⇒ピンクのタッセルペイズリーカットソー*Lablynth
 ボトム⇒ネイビースウェットマキシスカート*usagiYa
ボトム⇒ネイビースウェットマキシスカート*usagiYa
 ウェッジソールサンダル
ウェッジソールサンダル
お店に*SioMaNeKi*の服が出店されることもあり♪

お盆明け 営業再開しております(*^▽^*)
まだ夏物セール商品もありますが、
秋にも使えるものがあるので要チェックしてください♪
秋物 商品も続々と入荷中です(((o(*゚▽゚*)o)))21日に大量に秋物仕入れに行きます~(*^▽^*)
商品も続々と入荷中です(((o(*゚▽゚*)o)))21日に大量に秋物仕入れに行きます~(*^▽^*)
秋物といっても今でも着れる薄手のものがほとんど♪
また見に来てくださいね~*******
うさぎ屋
 で人気のく作家*le ciel*
で人気のく作家*le ciel*カラフル
*handmade*乙女なナチュラルレース蝶々*ヘアコーム*

オシャレなプレゼントに♪
ナチュラル
SWEET系(*/∀\*)
可愛い
*ハッピー♪

na乙女アクセがニクイ

可愛い個性派naいやし系
アンティーク感あり可愛いファッションのワンポイント♪に揃えたい****

ナチュラル
ナチュラルレースや蝶々のチャーム
 可愛い♪癒される カラーです(*/∀\*)
可愛い♪癒される カラーです(*/∀\*)
乙女心くすぐるパーツ
手が込んでる★

¥800

かわいい(ノ´∀`*)
*SioMaNeKi*も欲しい一品ですな~♪

*SioMaNeKi*の豆知識
*髪飾り*
わが国では、古代から髪を飾る習慣があり、頭に挿すものを髻華(うず)、あるいは挿頭華(かざし)といい、また頭に巻くものを鬘(かつら)とよんだ。当初は自然のままの植物の花を使ったが、のち金属製のものとなった。男の場合は603年(推古天皇11)わが国に冠位制度ができたおりから、元日に髻華をつけることになった。のち皇子諸王諸臣はみな金髻華をつけたが、この制度が複雑化するにつれて銀、銅などが加わった。平安時代に宮中の年中行事が確立するとともに、宮中参内のおりに草花を飾りとしたが、冠や烏帽子(えぼし)の生活が日常化するにつれて、頭髪よりも被(かぶ)り物に飾りとしてつけた。もちろん、儀式、官位、身分によって一定の決まりがあった。
女性の場合は、飛鳥(あすか)・奈良時代に衣服令が定められて、礼服を着用するおりには宝髻(ほうけい)にしたが、平安時代以降になって、盛儀のときに着用する女房晴装束には、髪上げをしてから釵子(さいし)を飾りとした。庶民生活のなかで髪飾りが用いられるようになったのは、下げ髪にかわって、髷(まげ)のある髪形ができた江戸時代からである。まず最初に櫛(くし)、笄(こうがい)、簪(かんざし)が挿され、これに加えて手絡(てがら)、丈長紙(たけなががみ)、根掛(ねがけ)、はね元結(もとゆい)などが用いられた。遊里における花魁(おいらん)の姿の華やかさから、町人の粋姿(いきすがた)にまで髪飾りはその一役を担ったのである。
明治になり、日本髪より束髪が流行するようになって、日本的な髪飾りは一時減少した。明治末から大正初期にかけては松井須磨子(すまこ)が演じた『復活』にちなんで、ゴムの輪櫛(わぐし)が「カチューシャ」とよばれてふたたび少女たちの間で大流行した。第一次世界大戦後は断髪の流行やパーマネント・ウエーブの普及の余波を受けて、急速に髪飾りは減っている。しかし、正月などの晴れ着を着る際に新日本髪には髪飾りとしての花簪(はなかんざし)は必需品であり、打掛(うちかけ)姿の花嫁衣装には欠かせないものの一つでもある。
★インタネット引用より
昨日の*SioMaNeKi*ふぁっしょんは、
「 *ピンクnaアマゾネス?!*」
 トップス⇒ピンクのタッセルペイズリーカットソー*Lablynth
トップス⇒ピンクのタッセルペイズリーカットソー*Lablynth ボトム⇒ネイビースウェットマキシスカート*usagiYa
ボトム⇒ネイビースウェットマキシスカート*usagiYa ウェッジソールサンダル
ウェッジソールサンダルお店に*SioMaNeKi*の服が出店されることもあり♪

お盆明け 営業再開しております(*^▽^*)
まだ夏物セール商品もありますが、
秋にも使えるものがあるので要チェックしてください♪
秋物
 商品も続々と入荷中です(((o(*゚▽゚*)o)))21日に大量に秋物仕入れに行きます~(*^▽^*)
商品も続々と入荷中です(((o(*゚▽゚*)o)))21日に大量に秋物仕入れに行きます~(*^▽^*)秋物といっても今でも着れる薄手のものがほとんど♪
また見に来てくださいね~*******

Posted by *SioMaNeKi* at 16:39│Comments(0)
│★うさぎ屋no本日おススメ商品★