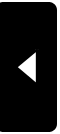2013年03月28日
いろいろ付けれる♪手作り*カラフルnaturalなフラワーコサージュ
★本日のおススメ商品★
うさぎ屋 NEW!入荷人気のナチュラル系麻ひも編み作家*Bous* さん
NEW!入荷人気のナチュラル系麻ひも編み作家*Bous* さん
新作★
いろいろ付けれる♪
ハンドメイド『カラフルnaturalなフラワーコサージュ』

handmade コーナー から
ナチュラルGoods
の一品に♪
お気に入りの♪
アクセサリー
プレゼントに♪
ハンドメイドの*ぬくもり*が
伝わる
ガールnaアイテム

麻ひもBAGのお供にも
乙女noお花モチーフ
BAGや洋服との相性バッチシ♪とても可愛い(((o(*゚▽゚*)o)))
カラフルないろんなバージョンのお花コサージュ♪、モチーフがレースなど乙女心満載の組み合わせがいっぱい♪になって登場!
¥450,¥500
めちゃ可愛い

*SioMaNeKi*もすぐ購入しました!
わたしが選んだのは、パープル系♪リーズナブルで、自然体で、可愛い♪
うさぎ屋 で新作ですが、とっても良く売れてるハンドメイドアクセサリーです(*/∀\*)

*SioMaNeKi*が購入したコサージュ♪洋服ベストにも♪トートBAGにも♪どちらにも合うよ(*^▽^*)

 *SioMaNeKi*の豆知識
*SioMaNeKi*の豆知識
*お花見*
★花見の歴史★
花見は奈良時代の貴族の行事が起源だといわれる。奈良時代には中国から伝来したばかりの梅が鑑賞されていたが、平安時代に桜に代わってきた。それは歌にも現れており、『万葉集』には桜を詠んだ歌が40首、梅を詠んだ歌が100首程度みられるが、10世紀初期の『古今和歌集』ではその数が逆転している。「花」が桜の別称として使われるのもこの頃からである。
『日本後紀』には、嵯峨天皇が812年(弘仁3年)に神泉苑にて「花宴の節(せち)」を催したとある。時期的に花は桜が主役であったと思われ、これが記録に残る花見の初出と考えられている。831年(天長8年)からは宮中で天皇主催の定例行事として取り入れられた。その様子は『源氏物語』「花宴(はなのえん)」にも描かれている。
吉田兼好は『徒然草』第137段で、身分のある人の花見と「片田舎の人」の花見の違いを説いている。わざとらしい風流振りや騒がしい祝宴に対して冷ややかな視線であるが、ともあれ『徒然草』が書かれた鎌倉末期から室町初期の頃にはすでに地方でも花見の宴が催されていたことが伺える。
織豊期には野外に出て花見をしたことが、絵画資料から確認される。この時期のもっとも大規模な花見は1598年(慶長3年)3月15日に行われた豊臣秀吉の醍醐の花見である。
花見の風習が広く庶民に広まっていったのは江戸時代といわれる。江戸でもっとも名高かったのが忍岡(しのぶがおか)で、天海大僧正によって植えられた寛永寺の桜である。しかし格式の高い寛永寺で人々浮かれ騒ぐことは許されていなかったため、享保年間に徳川吉宗が浅草(墨田川堤)や飛鳥山に桜を植えさせ、庶民の行楽を奨励した。江戸の城下・近郊の花見の名所は上野寛永寺、飛鳥山、隅田川堤の他にも、愛宕山、玉川上水など少なからずあった。この時期の花見を題材にした落語としては、『長屋の花見』や『あたま山』、飛鳥山の花見を想定して作られた『花見の仇討(あだうち)』などがある。
★インタネット引用より
本日の*SioMaNeKi*ふぁっしょんは、
イメージタイトル
「 *日曜日はフリマへ* 」
 ベスト⇒デニムのボーイズベスト
ベスト⇒デニムのボーイズベスト
 トップス⇒お花のガーリーニット*FRUITCAKE
トップス⇒お花のガーリーニット*FRUITCAKE
 ボトム⇒ピンクのエスニックマキシスカート*earth & ecology
ボトム⇒ピンクのエスニックマキシスカート*earth & ecology
 厚底スニーカー
厚底スニーカー
うさぎ屋
 NEW!入荷人気のナチュラル系麻ひも編み作家*Bous* さん
NEW!入荷人気のナチュラル系麻ひも編み作家*Bous* さん新作★
いろいろ付けれる♪
ハンドメイド『カラフルnaturalなフラワーコサージュ』

handmade コーナー から
ナチュラルGoods
の一品に♪
お気に入りの♪
アクセサリー
プレゼントに♪

ハンドメイドの*ぬくもり*が

伝わる

ガールnaアイテム

麻ひもBAGのお供にも
乙女noお花モチーフ
BAGや洋服との相性バッチシ♪とても可愛い(((o(*゚▽゚*)o)))
カラフルないろんなバージョンのお花コサージュ♪、モチーフがレースなど乙女心満載の組み合わせがいっぱい♪になって登場!

¥450,¥500

めちゃ可愛い


*SioMaNeKi*もすぐ購入しました!
わたしが選んだのは、パープル系♪リーズナブルで、自然体で、可愛い♪
うさぎ屋 で新作ですが、とっても良く売れてるハンドメイドアクセサリーです(*/∀\*)

*SioMaNeKi*が購入したコサージュ♪洋服ベストにも♪トートBAGにも♪どちらにも合うよ(*^▽^*)


 *SioMaNeKi*の豆知識
*SioMaNeKi*の豆知識
*お花見*
★花見の歴史★
花見は奈良時代の貴族の行事が起源だといわれる。奈良時代には中国から伝来したばかりの梅が鑑賞されていたが、平安時代に桜に代わってきた。それは歌にも現れており、『万葉集』には桜を詠んだ歌が40首、梅を詠んだ歌が100首程度みられるが、10世紀初期の『古今和歌集』ではその数が逆転している。「花」が桜の別称として使われるのもこの頃からである。
『日本後紀』には、嵯峨天皇が812年(弘仁3年)に神泉苑にて「花宴の節(せち)」を催したとある。時期的に花は桜が主役であったと思われ、これが記録に残る花見の初出と考えられている。831年(天長8年)からは宮中で天皇主催の定例行事として取り入れられた。その様子は『源氏物語』「花宴(はなのえん)」にも描かれている。
吉田兼好は『徒然草』第137段で、身分のある人の花見と「片田舎の人」の花見の違いを説いている。わざとらしい風流振りや騒がしい祝宴に対して冷ややかな視線であるが、ともあれ『徒然草』が書かれた鎌倉末期から室町初期の頃にはすでに地方でも花見の宴が催されていたことが伺える。
織豊期には野外に出て花見をしたことが、絵画資料から確認される。この時期のもっとも大規模な花見は1598年(慶長3年)3月15日に行われた豊臣秀吉の醍醐の花見である。
花見の風習が広く庶民に広まっていったのは江戸時代といわれる。江戸でもっとも名高かったのが忍岡(しのぶがおか)で、天海大僧正によって植えられた寛永寺の桜である。しかし格式の高い寛永寺で人々浮かれ騒ぐことは許されていなかったため、享保年間に徳川吉宗が浅草(墨田川堤)や飛鳥山に桜を植えさせ、庶民の行楽を奨励した。江戸の城下・近郊の花見の名所は上野寛永寺、飛鳥山、隅田川堤の他にも、愛宕山、玉川上水など少なからずあった。この時期の花見を題材にした落語としては、『長屋の花見』や『あたま山』、飛鳥山の花見を想定して作られた『花見の仇討(あだうち)』などがある。
★インタネット引用より
本日の*SioMaNeKi*ふぁっしょんは、
イメージタイトル

「 *日曜日はフリマへ* 」
 ベスト⇒デニムのボーイズベスト
ベスト⇒デニムのボーイズベスト トップス⇒お花のガーリーニット*FRUITCAKE
トップス⇒お花のガーリーニット*FRUITCAKE ボトム⇒ピンクのエスニックマキシスカート*earth & ecology
ボトム⇒ピンクのエスニックマキシスカート*earth & ecology 厚底スニーカー
厚底スニーカー
梅春物★LIME.INC新作多数入荷!!明日は更に!10%OFFセール★古着②倍ポイントなど♪
NARUオンライン展示会★2階掘り出し市バージョンアップ↑春物30%offセール!コレ当たりました写真&いろいろ写真♪
うさぎ屋セレクト6月まぐかっぷ展開催中!パッチワークスカートやM.M.Oナチュラル服新作入荷★刺繍猫
土曜限定!NARUオンライン展示会★最新LIME.INC&Scolar&モード系倶楽部など刺繍ブローチ♪
北欧デザイン春夏新作Emago.いろいろ入荷NARUボーダー★モード系アクセサリーなど♪母の日ギフト
NARU最新カタログ到着★サイコロセールパワーアップやNARU春40%OFFセール&春新作多数入荷ARY
NARUオンライン展示会★2階掘り出し市バージョンアップ↑春物30%offセール!コレ当たりました写真&いろいろ写真♪
うさぎ屋セレクト6月まぐかっぷ展開催中!パッチワークスカートやM.M.Oナチュラル服新作入荷★刺繍猫
土曜限定!NARUオンライン展示会★最新LIME.INC&Scolar&モード系倶楽部など刺繍ブローチ♪
北欧デザイン春夏新作Emago.いろいろ入荷NARUボーダー★モード系アクセサリーなど♪母の日ギフト
NARU最新カタログ到着★サイコロセールパワーアップやNARU春40%OFFセール&春新作多数入荷ARY
Posted by *SioMaNeKi* at 15:58│Comments(0)
│うさぎ屋『*handmade*アクセサリー小物』