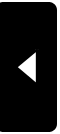2014年05月05日
*handmade*カラフルポップnaランドセル小物入れフェルト雑貨
 うさぎ屋の商品(洋服:ハンドメイド商品:小物:バッグ)いろいろ追加で
うさぎ屋の商品(洋服:ハンドメイド商品:小物:バッグ)いろいろ追加でうさぎ屋ネットショップに出品中です!のぞいてみてくださいね♪
うさぎ屋ネットショップ⇒

 http://usagiya3377.shop-pro.jp/
http://usagiya3377.shop-pro.jp/ facebookもあります!『うさぎ屋』で検索可能◎
facebookもあります!『うさぎ屋』で検索可能◎※宜しければ、【いいね!】をよろしくお願いしますm(・^・)m
うさぎ屋は、連休中は明日6日祝日も営業しておりますので、見に来てくださいね♪ヽ((◎´∀`◎))ノ゚
★7日以降も通常営業です(*^▽^*)
★本日のおススメ商品★
うさぎ屋
 で人気の♪革&和雑貨+インテリア雑貨 作家の*みつこ*さん
で人気の♪革&和雑貨+インテリア雑貨 作家の*みつこ*さん*handmade*
可愛い♪
カラフルポップnaランドセル小物入れフェルト雑貨

handmade コーナー から
フェルト雑貨GOODS
お手頃価格でお気に入りの小物に揃えたい****

★みつこ★
可愛い~いやし系(*/∀\*)

フェルト雑貨(*/∀\*)

大人のインテリアや、
子供が遊ぶのにも大人気

¥500

メチャ安い!
いろんなお色があって、どの色にしようか迷う(*^▽^*)

オシャレで楽しい
*インテリア小物雑貨*

プレゼントにもなかなかない商品なので、喜ばれるかも(ノ´∀`*)


*SioMaNeKi*
 も
も欲しい一品ですナ~

その他のお色ありますよ(ノ´∀`*)↓

*SioMaNeKi*の豆知識
ランドセルの歴史
江戸時代(幕末)、幕府が洋式軍隊制度(幕府陸軍)を導入する際、将兵の携行物を収納するための装備品として、オランダからもたらされた背嚢(はいのう、バックパック])のオランダ語呼称「 ransel(オランダ語版)」(「ランセル」または「ラヌセル」)がなまって「ランドセル」になったとされ[1][3][4]、幕末の教練書である『歩操新式』の元治元年(1864年)版(求實館蔵板)にも「粮嚢」の文字に「ラントセル」の振り仮名がされているほか、画像としては一柳斎国孝筆の双六「調練仕方出世寿語禄」(版元・大黒屋金三郎)に描かれている、韮山笠を被った兵士が背負っている鞄がそれとみられる。これは昭和前期までの通学用ランドセルに形状がよく似ており、この背嚢がルーツであることがわかる
明治時代以降、本格的な洋式軍隊として建軍された帝国陸軍においても、歩兵など徒歩本分者たる尉官准士官見習士官[5]、および下士官以下用として革製の背嚢が採用された。
通学鞄としての利用は、官立の模範小学校として開校した学習院初等科が起源とされている。創立間もない1885年(明治18年)、学習院は「教育の場での平等」との理念から馬車・人力車による登校を禁止、学用品を入れ生徒が自分で持ち登校するための通学鞄として背嚢が導入されたが、当初はリュックサックのような形であった。1887年(明治20年)、当時皇太子であった大正天皇の学習院初等科入学の際、伊藤博文が祝い品として帝国陸軍の将校背嚢に倣った鞄を献上、それがきっかけで世間に徐々に浸透して今のような形になったとされる。贅沢な高級品であった事から戦前は都市部の富裕層の間で用いられる事が多く、地方や一般庶民の間では風呂敷や安価な布製ショルダーバッグ等が主に用いられていた。ランドセルが全国に普及したのは昭和30年代以降、高度経済成長期を迎えた頃からと言われる。
ランドセル側面にあるフックは、「軍用背嚢の名残で元は手榴弾を下げるため」という俗説がありTVでももっともらしく紹介されているが、これは昭和30年代に入り、給食袋や体育着袋など生徒の持ち物が増えた事に対応した金具である。実際の帝国陸軍において手榴弾は雑嚢(背嚢とは別のショルダーバッグ)に入れ携行され(戦闘時には軍服のポケットや腰の帯革も使用される)、そもそも活動時に重く邪魔になる背嚢は戦闘前に着脱される事が基本である。また、背嚢の周囲には毛布(下士官以下はさらに天幕・円匙等)を巻き付けるため手榴弾を下げる余裕はない。
ランドセルは小学校入学から卒業までの6年間使うのが基本となっており、市販されているものは6年間の保証付きになっていることが多い。しかし、傷みの進行や本人の好みの変化などによって、卒業前にランドセルの使用をやめる児童もいる。
欧米の学校でも似たようなものが使われている。ただし、ドイツの通学かばんSchulranzen、同オランダBoekentasなど、日本のランドセルに比べて素材は質素で軽いものが多い。
★インタネット引用より
本日の*SioMaNeKi*ふぁっしょんは、

イメージタイトル
「 *山に行こうか?海に行こうか?* 」
 トップス⇒レトロピンクのデザインチュニック*COCODEAL
トップス⇒レトロピンクのデザインチュニック*COCODEAL ボトム⇒ブルーペイント8分丈デニムパンツ*DENIM DUNGAREE
ボトム⇒ブルーペイント8分丈デニムパンツ*DENIM DUNGAREE ひも付きカヌーサボ
ひも付きカヌーサボお店に*SioMaNeKi*の服が出店されることもあり♪
Posted by *SioMaNeKi* at 13:27│Comments(0)
│うさぎ屋『*handmade*小物雑貨』